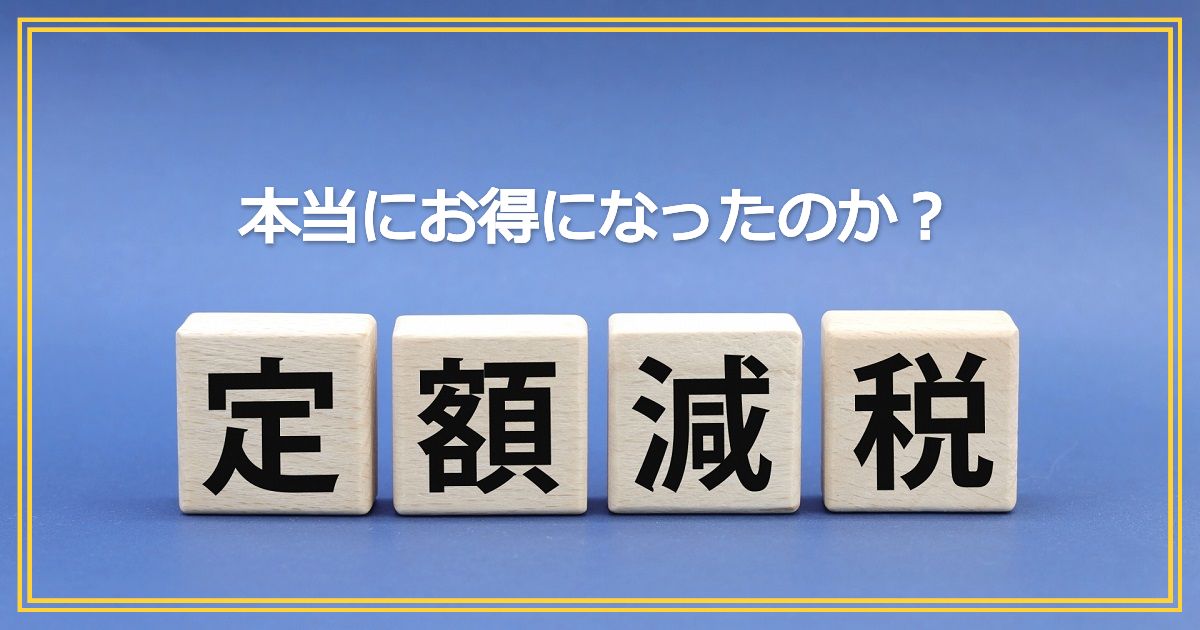かんう
かんう2024年6月給与より定額減税が始まるぞ



兄貴!定額減税ってなんだ?



(所得税3万円・住民税1万円)×(自分+扶養人数分)の減税が受けれる制度だ
ついに2024年6月より始まる定額減税制度
国民にとって喜ばしい事なのか?はたまた何の効果も無い施策となってしまうのか?実際に対応に追われた中間管理職の僕が事務員目線で回答します
今後の増税予定も記載しているので貯蓄計画の参考にしてください
定額減税のおさらい
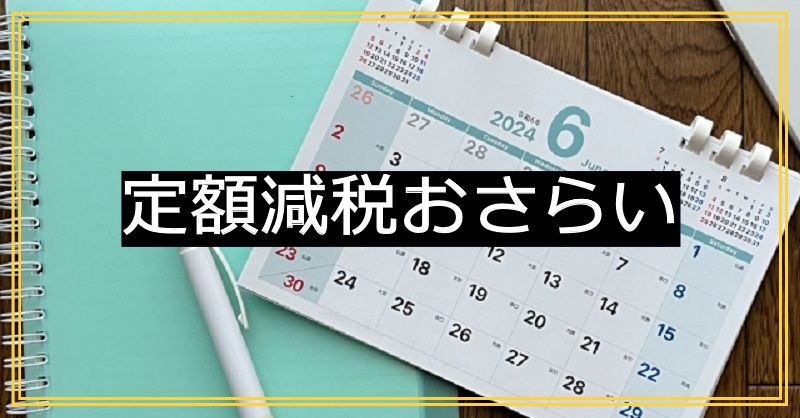
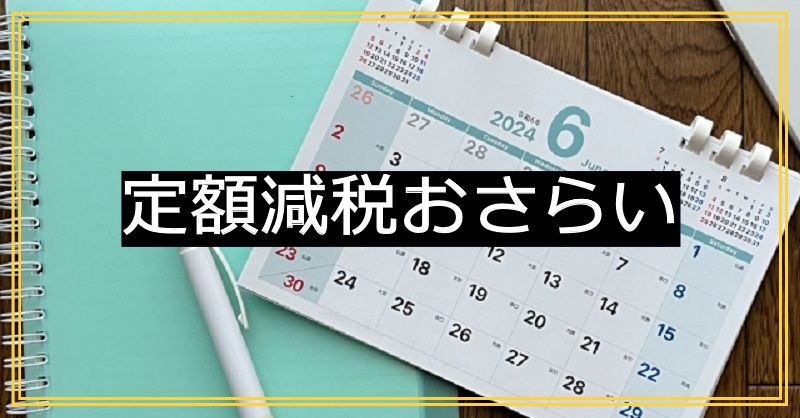
冒頭で軽く説明していますが定額減税のおさらいを記載
・実施時期:2024年6月
・減税額:(所得税3万円,住民税1万円)×(自分+扶養人数)
・(還付):上記減税額を使用しきれない場合は後に還付有り
・対象者:合計所得金額1,805万円以下の納税者と扶養者
・減税の目的:急激な物価高騰に対して収入が追い付いていないので緩和策
・次年度以降の継続性:現状不明(状況によっては来年以降も・・と自民党が発言)
これだけを見ると国民の為に十分なっている施策と見れますね
自分・配偶者・子供1人の世帯の場合は4万円×3名=12万円の減税を受けられる(扶養に入っている場合)ので2024年の家計は大変助かる計算となる(正確には住民税は2024年6月~2025年5月分)
でも国民全員が素直に喜べている訳ではありませんよね?
詳しくは次項で説明します
定額減税が素直に喜べない理由
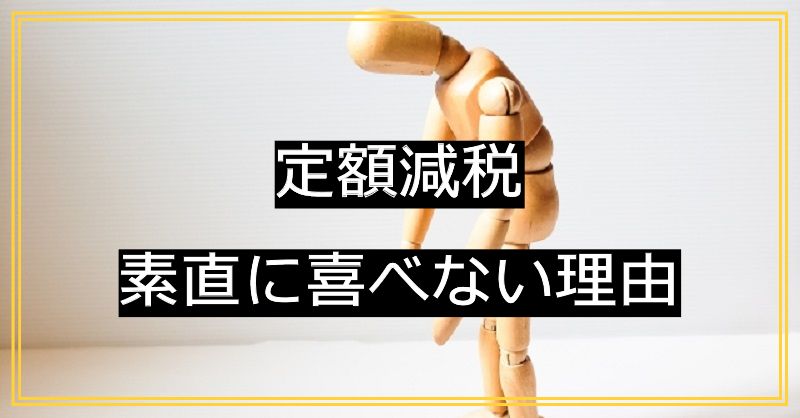
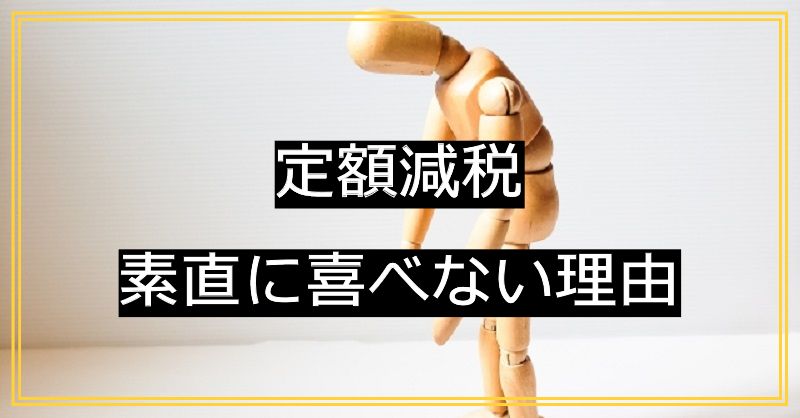
何個か世間の不満・不安内容を記載すると以下の通り
①今回限りの一時的な施策
②選挙対策
③事務員の手間が増える
④今後の増税・保険料値上げ
⑤結局給料が増えない
⑥更なる物価高騰
個人的問題は④と⑤と⑥ですね。この3点がネックで正直僕自身も喜べていません
それぞれ詳しく解説して行きましょう
今回限りの一時的な施策
おさらいには一応記載していますが来年度以降の施策に関しては現状不明です
一回限り・4万円ぽっちで今後の暮らしが楽になるか?当然不可!各議員達は国民の平均年収を理解していないのでは・・?と感じています
円安などの不安要素もあるので今だけでなく先を見通した施策をして欲しい
選挙対策
岸田総理の任期が2024年9月迄となっておりそれまでには国会で総理候補として再び入らなければ行けません
今の総理は増税関係の施策が多く、正直国民にとってはマイナスなイメージが付いているかと思われますよね。そこでついに国民にとってメリットのある施策
世間ではこれが選挙対策では無いかと言われてます(各国会議員のイメージアップにも同様に繋がるとお考えください)
個人的にはこれのおかげで自民党に投票する!という感情は一切ありませんが
事務員の手間が増える
yahooニュースなどで各記事を見て僕自身も思ったのですが、実際に業務を行っている身からすると確かに手間が増えて面倒ですがそこまでの手間が増えた印象では無いですね
何故そこまで各事務員が怒っているのか要因を記載
①そもそも定額減税についての勉強
②各社員に通知の義務化
③給与明細に定額減税額の記載義務
①の解説は省きますが②③を詳しく解説
各社員に通知の義務化
具体的な金額を各社員に通知する必要は無く、とにかく通知をすれば良いのでメールで一斉送信で問題無し
一度別の給与ソフトで参考例を見ましたが、A社員扶養人数○○人・減税額○○万円など細かい通知書を発行している物をあるようなので丁寧に発行したら手間がかかる要素ですね
給与明細に定額減税額の記載義務
例えば2024年6月給与の所得税関係の記載を例に
給与:○○円
源泉所得税:45,000円
定額減税額:▲30,000円
又は以下のように
給与:○○円
源泉所得税:15,000円(減税前:45000円・減税額:▲30,000円)
このように記載するように義務化が命じられました。この事から恩着せがましいと事務員担当から怒りの声が上がっているようですが大体の企業は給与ソフトを導入していると思うのでアップデートすれば簡単に対応出来るはず
実際に僕が対応したのは弥生給与のアップデート⇒給与明細に1項目(定額減税額)の反映程度の手順だったのでこの項目に関しては対して手間がかかりませんでした
手書きの給与明細だったら大変かと思いますがどちらかと言うと給与ソフト開発企業が大変だったかと
各役所の業務増加
突然の国からの通知で減税しなさいと言われたので住民税金額の計算が手間どったはず
例えば所得が○○で納付する住民税の金額は本来16万円だったとする
本来の住民税納付額:160,000円
減税額:▲10,000円
減税後納付額:150,000円
計算方法:2024年6月は一律0円(少額の場合は6月のみ発生)
(残りの2024年7月~2025年5月で150,000円を割り振る)
結果:2024年7月が14000円で残りの月が13600円。計150,000円となる
年収が高い人は従来通りですが一人一人計算方法も変わったので今回は役所の職員達も手間が増えたと嘆いている事でしょう
今後の増税・保険料値上げ
いくつかの例を挙げると以下の通り
・森林環境税(2024年4月)
・国民年金保険(2024年4月)
・国民健康保険(2024年度)
・たばこ税(2024年予定)
・社保及び雇用保険の加入要件拡充(2024年以降)
・扶養控除縮小(2026年以降)
・復興特別所得税の14年延期(元々2037年まで有り)
・法人税(2025年以降?)
・消費税15%(未定)
森林環境税は住民税が1万円減税と言われている傍ら年間1000円程度の増税となっています
実質住民税の減税は9,000円じゃないかと個人的に思いますが話題的には減税の1万円の方が強いので、実はこんな税金が発生しているのは知らない方も多いのでは無いでしょうか
たばこ税や法人税の増税は防衛費に宛がうと発表されておりますが、法人税に関してはただですら倒産する企業が増えているので会社が無くなれば生活出来なくなるので実質苦しい増税内容かと
結局給料が増えない
総理や他の国会議員が一番無責任なのがこの項目
昨今の物価高騰は企業努力で賃上げを行って対応しましょうとの事で企業次第ってのは憤りを感じている
資金力の無い企業は物価高騰で倒産及び業績悪化で賃上げに回せないなどの状況を良く聞くので、賃上げは行うが従業員を一部解雇などの判断も必要になってくる
しかし企業によっては財務省の調査によるとベアと定期昇給の賃上げ率5%以上を行った割合が36.5%・賃上げ自体を行ったのが大企業81.1%・中小企業63.1%と賃上げを行っている割合の方が多い
上記データは財務省調査の回答あった970社からの統計。2022年のデータでは従業員10人以上の企業は約44万社以上あるので該当しない方も多いので注意
従業員の定着を増やす為賃上げを行っている企業は実際には多いはずだが金額までは保証されないのが現状
更なる物価高騰
予測が出来ないが今後も値上げは必ず来ます
食料品・日用品・公共料金などの生活必需品が値上げとなるので生活が豊かになるかは不明。特に直近決まっている値上げ例は
電気代
国からの補助金が縮小及び終了により各家庭の電気代は一番の影響を受ける(値下げの電力会社も有り)
少なからず値上げの幅は約1,000円近くを見ておいた方がよいですが、詳しくまとめたサイトが株式会社エネテク様より挙がっているので参考


同様にガス代も国からの補助金が無くなってしまうので400円近く値上げ予定
結局定額減税は国民の為になったのか?
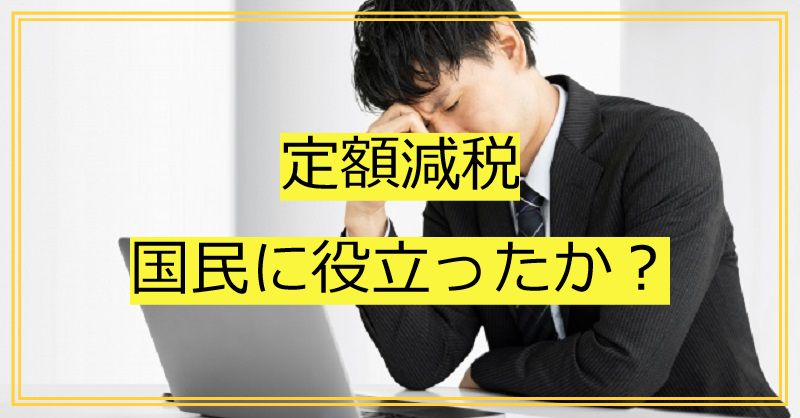
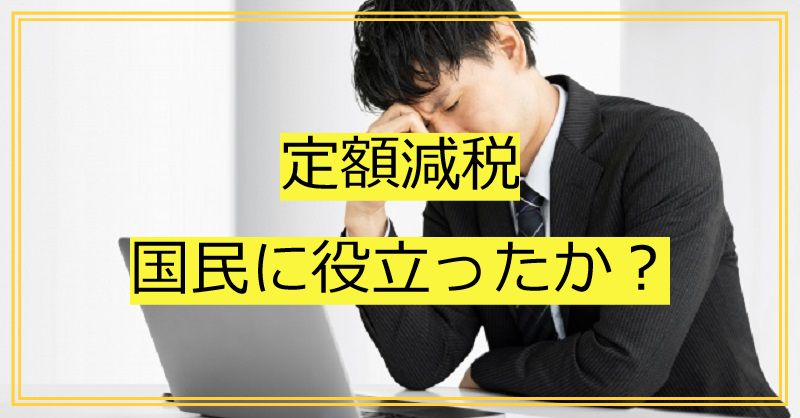
年収2000万以上の方は日本では約0.6%しかいないのでこの方達は元々対象外の為0.6%の国民からは意味のない施策となりました
前項の物価高騰でも記載していますが電気代・ガス代の補助金は無くなるので毎月1,500円近くは費用負担になる見込み。そこで40,000円÷1,500円=約27か月で減税分は無くなる計算となる
更に電気代・ガス代の単価値上げの可能性もあるので本当に一時的な施策。国の補助金で言えばガソリン代補助金も2024年6月で終了予定なので車を所持している方はガソリン代UPも想定出来る
そして国民の為になったか?
その解答は今だけ国民の為に役立ちました
将来的には意味は無くなるでしょう。他の物価高騰・増税が見込まれているので減税分の金額はすぐに支払った金額の方が上回ると思われます
個人的には社保や国保を恒久的に値下げする施策が一番喜ばれると思いますがその未来は訪れないですね・・
まとめ
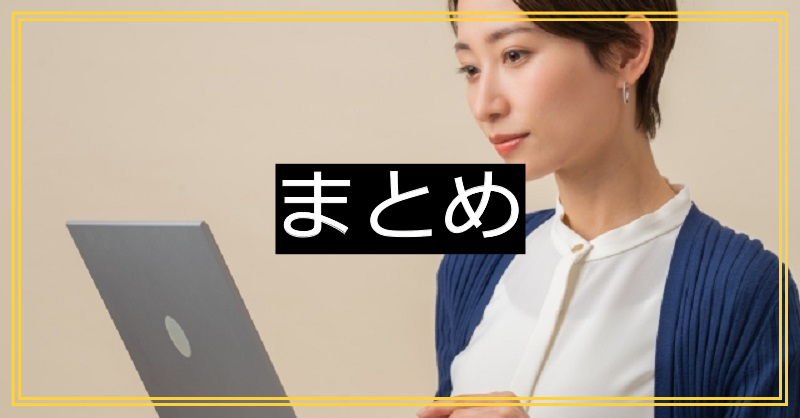
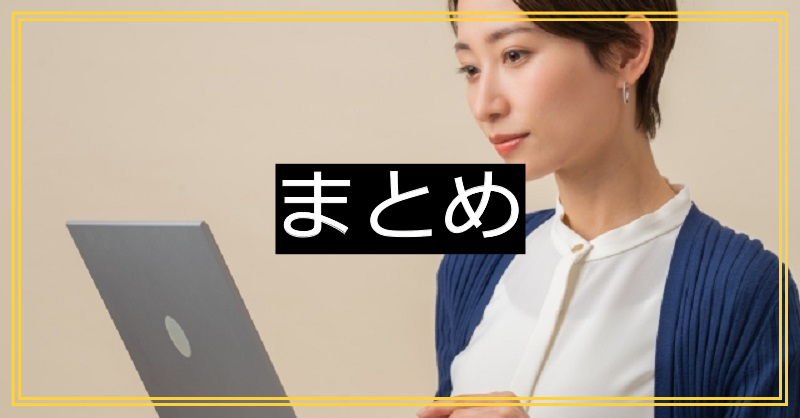
・定額減税は将来的には意味が無い
・4万円×(自分+扶養人数)が減税金額
・今後の増税や値上げが不安
・事務員の手間が増えて怒りの声が!
僕も業務として携わらなければここまで深くは考えなかったかもしれませんが、どうせ別の増税があるんでしょ?という感想が回りには多かったので素直に喜んでる方は少なかった
そこで資産運用にと考える方が増え2024年にはNISAの枠も拡充したので投資を始めて見た方が多いようです。皆さんも資産運用を始めていない方は検討されてはどうでしょうか?
NISAは自分の資産が必ずしも増える訳では無いので始める場合には注意